猫の慢性腎不全<診断・治療編>
猫の慢性腎不全:治療編
こんにちは、横須賀市にある「つだ動物病院」院長の津田航です。
前回のブログでは、猫の慢性腎不全の概要についてお伝えしました。
今回は、猫の慢性腎不全の、診断と治療に焦点を当ててお伝えしたいと思います。
なお今回も、前回と同様に猫の慢性腎臓病(CKD)も含めて猫の慢性腎不全としてお伝えしていきます。
猫の慢性腎不全の診断

まずは、慢性腎不全の診断についてです。
早期に慢性腎不全を発見するために有効な検査については前回のブログでも触れましたが、今回はもう少し詳しくお話ししたいと思います。
1. 血液学的検査
全血球検査(CBC)といって、機械などにより血液中の赤血球、白血球、ヘモグロビン、血小板などの数を調べたり、ヘマトクリット値(Ht値)といって、血液に占める赤血球の割合を算出したりして、貧血の有無や度合いを調べます。
腎機能が低下すると、増血ホルモンの分泌が抑制されて非再生性貧血になります。
非再生性貧血とは赤血球が作られなくなる貧血で、血液中に網状赤血球(まだ若い赤血球)が少なくなるのが特徴です。
2. 血液化学検査
腎機能の低下は、BUN(尿素窒素)、CRE(クレアチニン)、Ca(カルシウム)、IP(無機リン)、TP(総タンパク)などの値から診断します。
また最近では、SDMA(対称性ジメチルアルギニン)というアミノ酸の血中濃度が腎機能評価の指標として注目を浴びており、BUNやCREよりも早期に発見できると考えられています。
3. 画像検査
慢性腎不全の場合、一般的には腎臓の萎縮が起こったり腎臓の内部構造が不明瞭になったりするので、それを画像検査で確認します。
また、慢性腎不全という診断を行うためには、腎結石や水腎症、腎腫瘍ではないことを確認する必要もあります。
そのため、X線検査だけではなく超音波検査も含めて必要になります。
4. 尿検査
尿検査では、Ph値、ビリルビン、尿糖、潜血、尿タンパク、尿比重などが分かります。
中でも、慢性腎不全の場合は尿比重が低下することが多いので、尿比重は重要な指標です。
また、UPC(尿タンパク/クレアチニン比)が上昇している猫は予後が悪い傾向にあるので、UPCも大切な指標になります。
5. 組織学的検査
画像診断で腎臓が腫大している場合は、組織学的検査を行って腎臓腫瘍やリンパ腫の有無を確認する必要があります。
また、若齢の猫でCKDがみられる場合や高窒素血症がみられないにも関わらずUPCが継続的に高い値(>2.0)となる場合、CKDの猫でタンパク尿の悪化が認められる場合などにも行うことが推奨されています。
これらの検査により「腎機能が低下している」ことが1回分かっただけでは慢性腎不全という診断はできません。
継続的に検査を行い、3ヶ月以上持続的に腎臓がダメージを受けているとか、腎臓の糸球体濾過率が低下していることを確認できると、慢性腎不全だと診断することになります。
前回もお伝えしましたが、血液検査の結果に腎機能の異常が現れるのは、かなり腎機能の低下が進んでしまってからになります。
そのため、早期に発見するためには血液検査だけでは不十分です。
必ず、尿検査と画像検査も行う必要があるということを覚えておいて頂きたいと思います。
猫の慢性腎不全のステージ

慢性腎不全で腎機能が失われた腎細胞を再生させることはできません。
そのため、治療は完治ではなく、残っている腎機能をなるべく長く維持させることが目的になります。
IRIS(the International Renal Interest Society:国際獣医腎臓病研究グループ)という犬と猫の腎臓病に対する臨床獣医師の診断、理解、治療方法向上を目標に活動している団体があります。
その団体が、CKDのステージやステージ別の治療方法についてのガイドラインを出しています。
ここでは、IRISのガイドラインをベースに、慢性腎不全のステージや治療法について説明していきます。
<ステージ1>
【血液検査指標】
BUNなど:高窒素血症なし/CRE(mg/dl):<1.6/SDMA(μg/dl):>14
【尿検査指標】非蛋白尿(UPC<0.2)
【血圧】正常(<150)
【治療】
1. 可能な場合は腎毒性のある物質の投与をすべて中止する(薬剤も含めて)
2. 腎前性および腎後性の異常の有無を確認し、必要に応じて治療を行う
※腎前性:腎臓より前に問題がある=腎臓は働けるが血液が来ない状態
※腎後性:腎臓より後ろに問題がある=尿を作れるが出せない状態
3. 脱水の管理を行う
具体的には、「猫がいつでも新鮮な水を飲めるようにする」、「必要に応じて等張電解質輸液(乳酸リンゲル液など)を皮下投与または静脈内投与する」といったことを行います。
<ステージ2>
【血液検査指標】
BUNなど:軽度の高窒素血症/CRE(mg/dl):1.6~2.8/SDMA(μg/dl):>14
【尿検査指標】
非タンパク尿(UPC<0.2)または境界的なタンパク尿(UPC:0.2~0.4)
【血圧】正常(<150)または境界的な高血圧(150~159)
【治療】
基本的にはステージ1の治療に準じた治療を行い、腎臓病用の療法食による食事療法を開始します。
また、定期的に血圧の測定を行い、継続的に収縮期血圧が160mmHgを超えているような場合には高血圧の治療を開始します。
ステージ2の場合、正常な血漿リン濃度であることが多いのですが、まれに血漿PTH濃度が上昇している場合があります。
その場合は、リンの摂取を長期的に制限して、血漿リン濃度が4.6 mg/dl(1.5 mmol/L)以下になるように管理します。
代謝性アシドーシスが認められた場合は、適切な食事療法を行って状態を安定化させた後、薬剤の経口投与により適切な状態を維持できるよう管理します。
低カリウム血症がみられる場合も同様に、薬剤の投与による治療を行います。
また、痩せていてSDMAが25μg/dl以上の場合は、ステージ3の治療も検討します。
<ステージ3>
【血液検査指標】
BUNなど:中等度の高窒素血症/CRE(mg/dl):2.9~5.0/SDMA(μg/dl):中等度の上昇
【尿検査指標】
境界的なタンパク尿(UPC:0.2~0.4)またはタンパク尿(UPC>0.4)
【血圧】高血圧(160~179)または重度の高血圧(≧180)
【治療】
基本的にはステージ2の治療に準じた治療を行います。
脱水の管理は水の経口投与だけでは難しくなるため、定期的な等張電解質輸液の皮下または静脈内投与が必要になってきます。
一般的に、赤血球容積比(PCV)が20%以下になると、猫のQOL(生活の質)に影響が出ると言われていますので、貧血の治療を行います。
嘔吐、食欲減退、吐き気、体重減少といった症状が出てくるので、これらの症状に応じて制吐剤、食欲刺激剤、吐き気止めといった薬剤を投与します。
また、ステージ3の猫に腎臓から排泄される薬剤を投与する場合は、体内に蓄積しない用量に調節する必要があるため、慎重になる必要があります。
また、痩せていてSDMAが45μg/dl以上の場合は、ステージ4の治療も検討します。
<ステージ4>
【血液検査指標】
BUNなど:重度の高窒素血症/CRE(mg/dl):>5.0/SDMA(μg/dl):顕著な上昇
【尿検査指標】
タンパク尿(UPC>0.4)
【血圧】重度の高血圧(≧180)
【治療】
基本的にはステージ3の治療に準じた治療を行います。
タンパク質やカロリーの摂取不足に対する対策強化や脱水の予防対策強化が必要になるため、栄養チューブ(経皮的胃瘻チューブなど)の使用を検討します。
最終的には、透析や腎移植を検討します。
ただし、腎移植は腎不全以外の基礎疾患を持っていないこと、高齢猫の場合は術後生存率が悪くなる傾向があること等を考慮し、慎重に検討する必要があります。
猫の慢性腎不全の治療
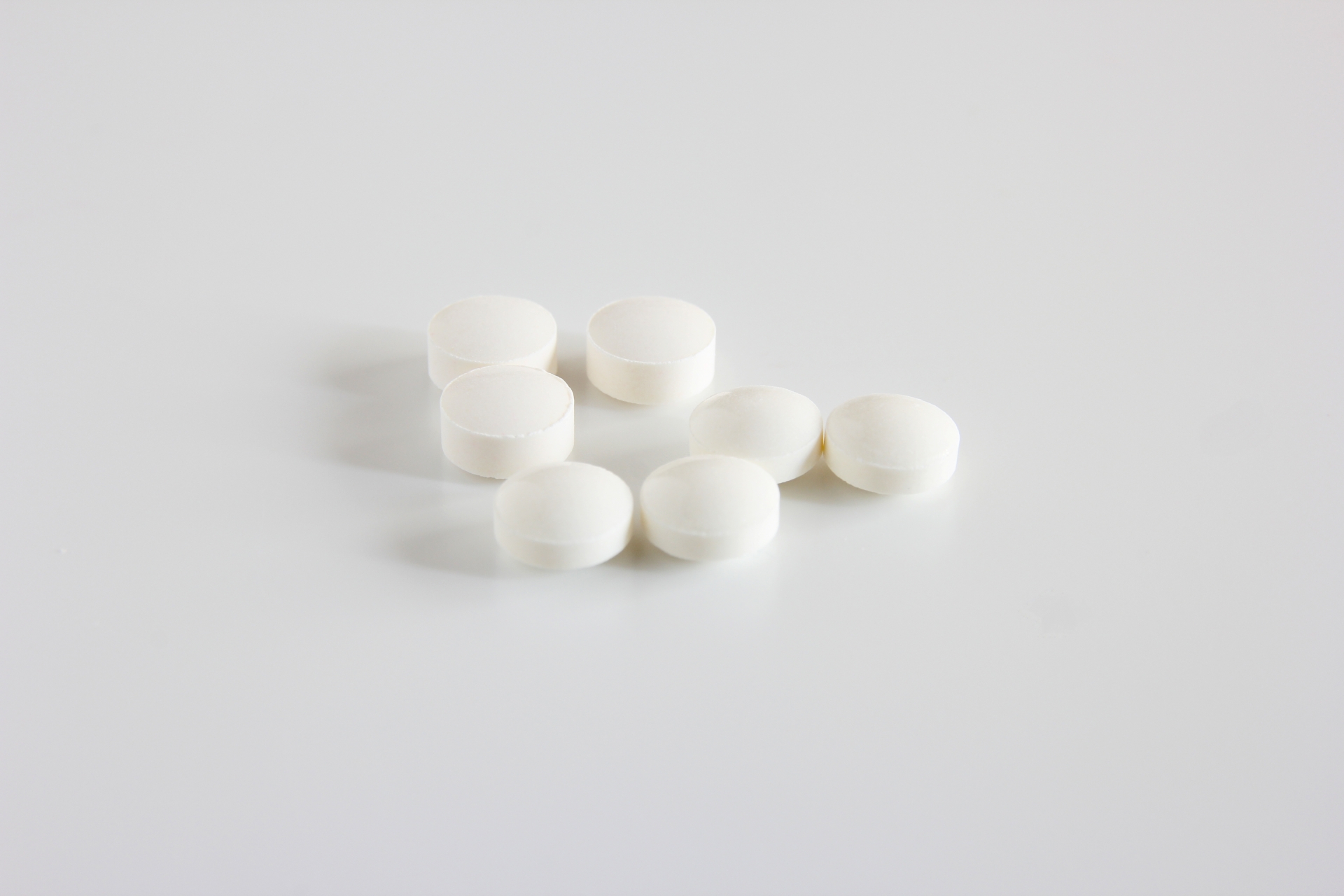
ではここで、慢性腎不全でよく使われる治療薬や療法食についてお話しします。
<慢性腎不全の治療薬>
1. フォルテコール
慢性腎不全における尿タンパクの漏出抑制に効果のある薬です。
腎臓の中にある糸球体の血圧を下げてタンパク尿や腎臓の負担を減らすことを目的としています。
薬の形状は錠剤ですが、猫の嗜好性を高めるためにフレーバーが付けられています。
UPC>0.2の慢性腎不全の猫に対する選択肢になり、UPCが0.2未満の猫に対しては適応しません。
2. セミントラ
フォルテコールと同様に、慢性腎不全における尿タンパクの漏出抑制に効果のある薬です。
フォルテコールより特異的な作用を持つ、猫の腎臓病の治療薬として2014年から販売されています。
形状は液剤です。
フォルテコール同様、UPC>0.2の慢性腎不全の猫に対する選択肢になり、UPCが0.2未満の猫に対しては適応しません。
3. ラプロス
日本初のCKDによる腎臓の繊維化を抑制する薬として、2017年に発売されました。
形状は小さめの錠剤です。
IRISステージ2~3の腎機能低下抑制と症状の改善という、従来の薬よりも一歩踏み込んだ効能効果で認可を受けています。
慢性腎不全でUPCが0.2未満の猫や、タンパク尿の有無に関わらずIRISステージ2~3の猫に対する治療薬としての選択肢となります。
<療法食について>
猫の慢性腎不全の治療を大きく支える柱が療法食です。
タンパク質に含まれるリンが制限されています。
最近では、多くのメーカーから腎臓病療法食が販売されています。
形状も、ドライフード、缶詰、パウチタイプ等色々と揃っています。
複数のメーカーのさまざまなタイプの療法食を試してみて、愛猫が好んで食べる療法食を複数みつけておくことをおすすめします。
猫の場合、好んで食べていたフードであっても、ある日突然食べなくなるというようなことがあるからです。
好んで食べてくれる療法食を、適宜取替えながら食べさせると良いでしょう。
慢性腎不全の猫をケアする際の注意事項

最後に、愛猫が慢性腎不全になってしまった場合に飼い主様がご自宅でできる愛猫へのケアに関する注意点をいくつかお話しします。
1. 食餌について
治療の基本は療法食による食事療法です。
食事は療法食を中心として、おやつも含めて猫の腎臓に配慮してタンパク質とリンが制限されている食餌を与えるようにしてください。
最近は、猫の嗜好性が高いことで有名なおやつにも、腎臓の健康維持に配慮したものが出ています。
2. 投薬時の注意事項
薬の服用は、1日1回とか1日2回のように決められています。
これは、24時間おきとか12時間おきに飲ませることで、猫の体内での薬の濃度を一定に保ち、効果を持続させられるということなのです。
そのため、薬を飲ませる間隔は、獣医師からの指示に従って出来るだけ一定の時間をあけて飲ませるようにしてください。
飼い主様の生活サイクルなどもあり難しいかもしれませんが、獣医師に最低何時間はあけなければならないかを確認し、少なくともその時間はあけてから飲ませるようにしてあげてください。
3. 脱水の管理について
ご自宅では、いつでも愛猫に新鮮な水をたくさん飲めるように工夫をしてあげましょう。
しかし、いずれは飲水や食事による水分摂取だけでは足りなくなります。
そうなると、等張電解質輸液(乳酸リンゲル液など)の皮下補液や静脈内投与という輸液療法が必要になってきます。
安全に輸液を行うためには、頻繁に通院して頂くことが必要になります。
愛猫のQOLを維持し、寿命を延ばすために必要な治療であることをご理解頂き、きちんと通院して頂きたいと思います。